ラストワンマイルとは?軽貨物ドライバーにも関係する“配送の最終区間”を解説
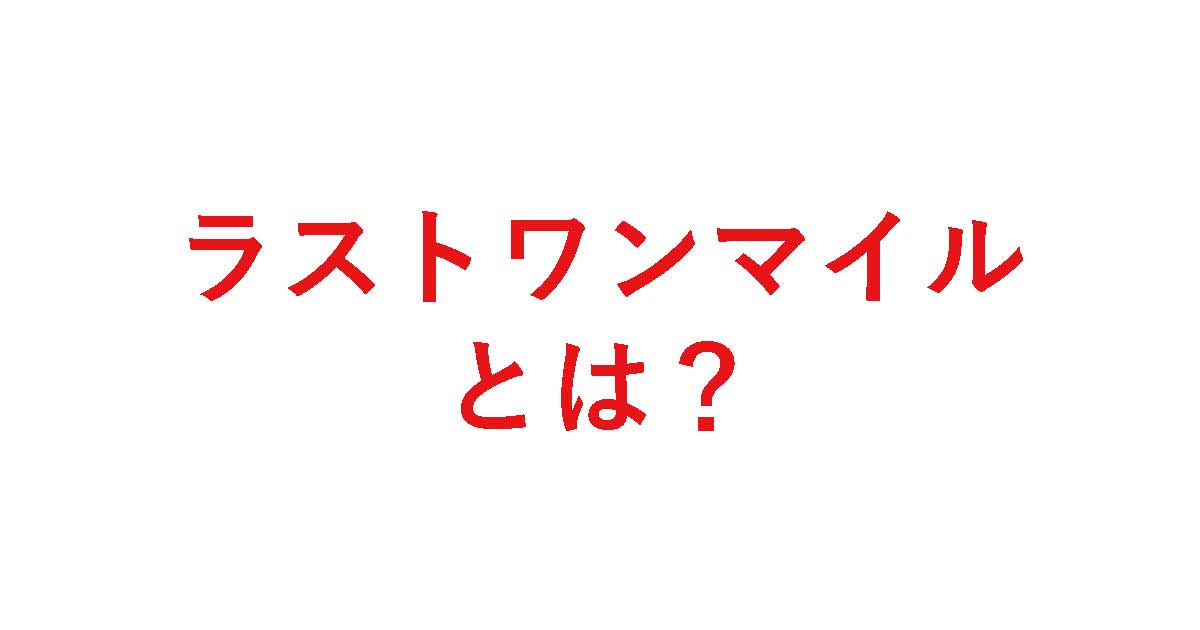
近年、「ラストワンマイル(Last One Mile)」という言葉を耳にする機会が増えました。物流業界や運送業界ではもちろん、ニュースやビジネス誌でも頻繁に取り上げられています。
ラストワンマイルとは、商品が物流センターや倉庫から最終目的地(主に消費者の自宅や指定先)に届けられる最後の区間を指します。この区間は、物流全体の中でも最も時間とコストがかかる部分であり、効率化が業界の大きな課題となっています。
最近では運送業界以外でも「ラストワンマイル=顧客接点部分」として使われることがあり、「最後に顧客と接するフェーズ」という意味で、営業・マーケティング領域にも広がっています。
ネット通販における「ラストワンマイル」の流れ
Amazonや楽天など、私たちが日常的に利用するネット通販。商品が注文されてから自宅に届くまでの流れを簡単に見てみましょう。
- 商品注文
顧客が通販サイト上で商品を選び、注文を確定します。 - 代金支払い
クレジットカードやコンビニ払いなどで決済が行われます。 - 倉庫からの出荷
商品は通販会社の倉庫(フルフィルメントセンター)から出荷されます。 - 配送会社への引き渡し
宅配業者に引き渡され、最寄りの営業所まで運ばれます。 - 営業所から自宅への配達(=ラストワンマイル)
ここが「ラストワンマイル」と呼ばれる区間です。 - お客様の受け取り
荷物が無事に届けられて、配達完了。
倉庫から営業所までの“幹線輸送”は大型トラックで一括輸送が可能ですが、最後の配達区間では住宅街や狭い路地を巡る必要があり、効率よりも柔軟性・丁寧さが求められます。
そのため、ラストワンマイルの現場では軽自動車・バイク・自転車・徒歩といった多様な配送手段が使われています。
「ラストワンマイル」が注目される理由
1. 顧客満足度を左右する最前線
配達スピードや時間指定の正確さ、丁寧な対応は顧客満足度に直結します。荷物を「確実に・迅速に」届けることが、ブランドイメージの向上にもつながります。
2. 物流コストの大部分を占める
ラストワンマイルは、全物流コストの約4〜5割を占めるともいわれます。そのため、ここを効率化することは企業にとって大きな経営課題です。
3. 社会的インフラとしての重要性
ネット通販が生活インフラとなった今、ラストワンマイルは“社会を動かす最後の線”。ドライバー1人ひとりの努力が、消費者の「便利な生活」を支えているのです。
ラストワンマイルが抱える課題
ドライバー不足と働き方の変化
EC市場の拡大により、宅配荷物は年々増加。一方で、ドライバーの高齢化・労働時間規制(いわゆる「2024年問題」)などで人手不足が深刻化しています。
その中で注目されているのが、業務委託型ドライバーという新しい働き方です。代表的な例が「Amazonフレックス」。個人事業主がアプリで案件を受注し、自分の都合に合わせて働ける仕組みで、柔軟な働き方を実現しています。
このような“シェアワーク型配送”は、今後ますます一般的になっていくでしょう。
配送料低下による「しわ寄せ」
通販各社の競争が激化し、「送料無料」をうたうサービスが一般化しました。しかし、実際には無料ではなく、誰かが負担しているのが現実です。
企業の値下げ圧力がドライバー報酬に直結し、「配達1個あたりの単価」が低下するケースも少なくありません。この構造的な課題が、現場の疲弊を生み出しています。
再配達問題と社会的コスト
再配達率は全国平均で約11〜12%といわれ、ドライバーが2度・3度と同じ家を訪れることも珍しくありません。
再配達にはガソリン代・時間・人件費がかかるうえ、報酬は「配達完了1件あたり」であるため、再訪しても収入は増えません。これが現場の大きなストレス要因です。
国も再配達削減に向けて「置き配」や「宅配ボックス」の利用促進を呼びかけています。再配達は、環境負荷の観点でも重要な社会問題といえるでしょう。
解決に向けた取り組みと技術革新
1. 身近な車両・手段の多様化
都市部では自転車・バイク・徒歩配送の導入が拡大。これにより、狭い住宅街でもスムーズに配達できるようになりました。さらに、自動車免許を持たない人でも配達員として働けるなど、雇用の裾野も広がっています。
2. AI・ルート最適化アプリの普及
AIが渋滞情報や地図データを分析し、最短ルートを自動提案。地図読みが苦手な人でも効率よく配達でき、作業時間の短縮につながっています。
3. 置き配・スマートロッカーの導入
再配達削減の切り札として、置き配・ロッカー受け取りが普及。不在時でも荷物を安全に届けることができ、顧客の利便性も向上しています。ただし、荷物の盗難や破損といったリスク対策も今後の課題です。
4. ドローン・自動配達ロボットの実証実験
ドローンは、山間部や離島での配送に活用されつつあります。また、都市部では自動配達ロボットの公道走行実験も始まりました。人手不足の解消や迅速な配送を目指す新しい試みとして、注目が高まっています。
「ラストワンマイル」は未来の物流を支える要
ラストワンマイルは単なる“最後の配送”ではなく、企業の信頼・顧客満足・環境配慮を支える重要なフェーズです。
軽貨物・個人ドライバーをはじめとした多くの人々がこの最前線を支え、AIやIoTなどの新技術が現場を支援しています。効率化と人間らしいサービスの両立こそ、これからの物流に求められる姿です。
「最後の1マイル」が社会を動かす
ラストワンマイルの現場は、まさに社会の血流。一つひとつの荷物が、誰かの暮らしを支えています。技術革新や制度改革が進む中で、現場の声を大切にしながら、「人とテクノロジーが共存する物流」を築いていくことが求められています。







