ライドシェア「Uber Japan株式会社」について調べてみた【ウーバーイーツとも関係あり】
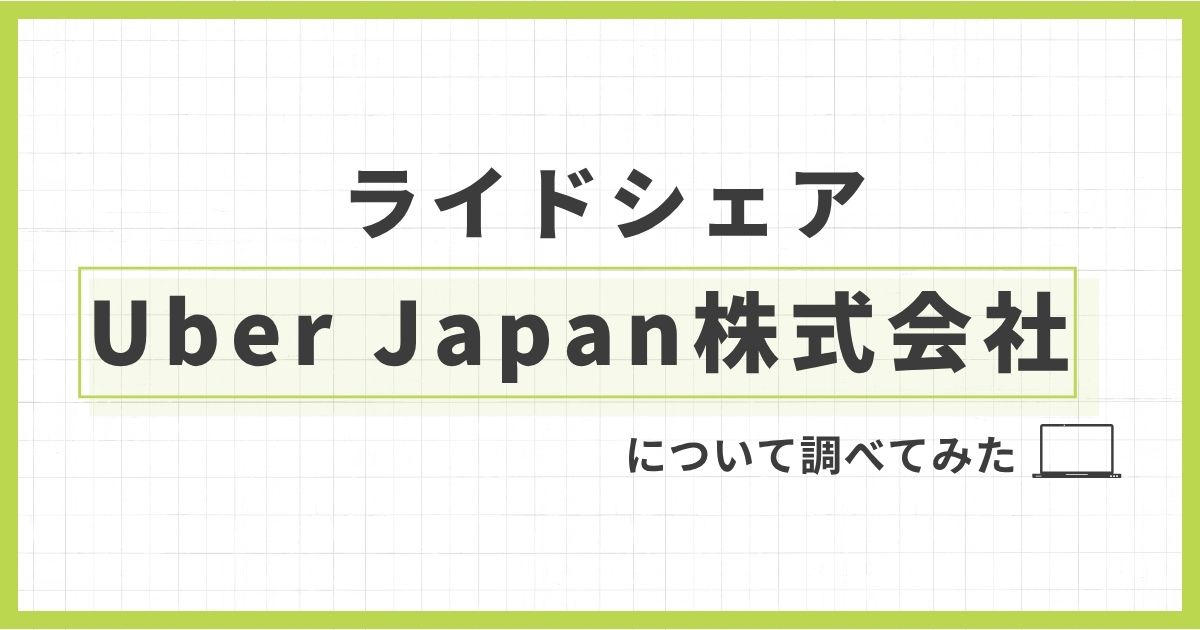
今回はライドシェア「Uber Japan株式会社」について調べてみました!
ライドシェアってどういった企業が参入するの?と気になっている方も大勢いるかと思います。
- Uberが何でライドシェアに関係するの?
- ウーバーイーツなら分かるけど、Uberを知らない
- Uberとウーバーイーツの関係性は?
と、こういった悩みを解決できる記事です。
ぜひご覧ください!
Uber(ウーバー)って何?基本情報
先日の記事でも触れましたが、「ライドシェア」とは車の相乗りを意味します。その中でも、世界的にライドシェアの象徴的存在となっているのが「Uber(ウーバー)」です。
Uberの仕組みや影響を理解するには、まず海外のライドシェア事情を知ることが重要です。なぜなら、日本ではまだ実証実験や規制緩和の段階にとどまっている一方で、海外ではすでにライドシェアが「日常の交通インフラ」として根付いているからです。
アメリカをはじめ、ヨーロッパ・東南アジア・オセアニアなど、世界各国でUberは一般的な移動手段のひとつとなっています。専用アプリを使えば、近くにいるドライバーを数分で呼び出すことができ、料金も自動計算され、支払いまでアプリ内で完結。利用者にとってはタクシーよりも手軽でスピーディーな移動手段として受け入れられています。
つまり、「Uber=ライドシェアの代名詞」といっても過言ではありません。Uberが築いた仕組みこそが、世界中でライドシェア文化を広げるきっかけとなったのです。
それでは、Uberがどのように誕生し、どのように世界へ広がっていったのか?
次に、その歴史と仕組みを見ていきましょう。
海外Uber(ウーバー)の会社概要
- 社名:Uber Technologies, Inc.
- フリガナ:ウーバー・テクノロジーズ
- 設立:2009年
- 所在地:アメリカ合衆国(サンフランシスコ)
- コーポレートサイト(会社概要):https://www.uber.com/jp/ja/about/
- 2022年売上:約4兆7,809億円
- 2022年最終益:約-1兆3,709億円
- 2023年売上:約5兆5,914億円
- 2023年最終益:約2,815億円
※ここではわかりやすく日本円に変換しています。
Uberの黒字化と赤字の意味
Uberは2023年、ついに黒字化を達成したことで大きな話題を呼びました。それまで長年にわたって赤字を続けてきた同社ですが、売上高は年々拡大し、ついに収益面でもプラスへ転じたのです。
注目すべきは、単に売上が大きいという点だけでなく、「これまでの赤字額の大きさ」にあります。一見すると「経営が上手くいっていなかったのでは?」と思われがちですが、実際にはその赤字こそが戦略的な投資の結果なのです。
ビジネスの世界では、赤字にもいくつかの意味があります。たとえばUberのように、圧倒的な資金を投入して市場を開拓・拡大している段階では、一時的な赤字=市場シェアの獲得コストと見ることができます。
つまり、利益を削ってでもユーザー数・ドライバー数・エリア展開を広げることで、将来的な収益の基盤を築いているのです。
この構図を誤解している人も少なくありません。シンプルに考えてみましょう。
もしあなたが同業のライドシェア企業だとして、Uberのように赤字覚悟でサービス価格を下げ、利便性を極限まで高めている競合と戦うとしたらどうしますか?おそらく、同じ価格設定では採算が取れず、太刀打ちできないはずです。
つまり、Uberの“赤字”とは「勝てないほどの投資で市場を取りにいく」という独自の成長戦略の証でもあります。この段階を経て、ユーザーとドライバーの両面で圧倒的なシェアを獲得した結果、ようやく黒字化へと転じた、それが2023年のニュースの背景です。
もちろん、今後は持続的な収益モデルへの移行やコスト最適化が求められますが、少なくともこの赤字期を経たことが、現在のUberの世界的なポジションを支えていることは間違いありません。
※あくまで主観的な分析ですが、これは「投資型成長戦略」の典型的な成功例といえるでしょう。
Uber(ウーバー)はどの市場を狙っているのか?
これまでに売上規模や成長戦略を見てきましたが、では実際にUberはどのような市場領域を狙っているのでしょうか。
その答えのひとつが、皆さんもおなじみの「Uber Eats(ウーバーイーツ)」にあります。
Uberのビジネスモデルの中核は、経費やリソースを“シェア”するためのマッチングプラットフォームです。アプリを通じて、移動したい人と運転できる人、食事を届けたい店と受け取りたい利用者、それぞれをつなぎ、巨大な経済圏を築いています。
Uberが展開する主なサービスは以下のとおりです。
- ライドシェア(Uber / UberXなど)
一般ドライバーと乗客をマッチングする、次世代型の配車サービス。
タクシーよりも柔軟で、移動の最適化・時間短縮を実現。 - 食品配達「Uber Eats(ウーバーイーツ)」
飲食店と配達パートナーを結ぶデリバリープラットフォーム。
自宅やオフィスで手軽に食事を注文できる仕組みを確立。
これらのサービスは現在、世界78カ国以上・数千の都市で展開されており、まさに「グローバルライドシェア企業」の代表格といえます。特にライドシェア事業は圧倒的な規模を誇り、アメリカ国内で約68%のシェアを占有しています。
また、世界中の月間アクティブユーザーは約9,300万人にのぼり、そのネットワーク規模は他社の追随を許しません。
一方で、日本国内ではまだ規制が厳しく、Uberが本来得意とするライドシェア事業は本格的に展開できていません。
現在のところ、国内で広く展開されているのは「Uber Eats」が中心です。しかし、近年のライドシェア規制緩和の議論を踏まえると、Uberが日本市場へ本格参入する日はそう遠くないでしょう。
もし法的な制約が解かれれば、Uberはその圧倒的な技術力とスピードで、一気に国内シェアを拡大する可能性があります。その瞬間、日本の移動インフラや働き方は、世界水準のスピードで変化していくことになるかもしれません。
Uberの日本法人
Uberは先に紹介した企業とは別に、日本法人を設立しています。
ここでは、それらをまとめてご紹介します。
Uber Japanの会社概要
- 社名:Uber Japan株式会社
- フリガナ:ウーバージャパン
- 所在地:東京都港区六本木1-9-10
- コーポレートサイト(会社概要):https://www.uber.com/jp/ja/about/
- Uber Eatsサービスサイト:https://www.ubereats.com/jp
- 国税庁 法人番号公表サイト:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=8010401103046
コーポレートサイトはUberと同じものとなります。日本語verをウーバージャパンとして使用しているのかもしれません。
Uber Eats Japanの会社概要
- 社名:Uber Eats Japan合同会社
- フリガナ:ウーバーイーツジャパン
- 所在地:東京都港区六本木1-9-10
- 国税庁 法人番号公表サイト:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=8010401103046
Uber Eatsの利用規約を見るとUber Japan株式会社となっていますので、サービスサイトはUber Japanの会社概要に載せております。旧名称は「Uber portier Japan合同会社(ウーバーポルティエジャパン)」となります。
余談ですが、「portier」を和訳すると「門番やドアマン」になります。出入口を管理する人を指しますが、シェアする守衛の仕組みを作ろうとしたのでしょうか?
Uberサイト内のニュースで、Uber Eats Japan合同会社として出している記事もあるため、他企業ではないようです。
Uber Eats にアカチャンホンポが登場 国内初、ベビー用品専門店からデリバリー開始の最新ニュース | Uber ニュースルーム
ライドシェアまずはタクシー会社の支援から
Uber Japan 株式会社(以下、Uber Japan)は 2024 年 1 月 26 日(金)、移動の足が不足する地域において開始される、タクシー会社による自家用車・ドライバーを活用した運送サービス(以下、タクシー会社によるライドシェア)の導入支援を 2024 年 4 月より開始し、本運送サービスの導入を希望する全国のタクシー会社と協議を始めることを発表しました。
出典:Uber Newsroom
この動きは、国が進めている「タクシー会社の管理下で限定的にライドシェアを緩和する制度」に沿ったものでしょう。
完全自由化ではなく、まずは既存のタクシー事業者を中心にライドシェア運用を始め、安全性や運行管理体制を確立した上で、段階的に拡大していく方針が見えてきます。
最初のステップとしては、Uberがタクシー会社へのシステム提供・運行支援を行い、各地でライドシェア運用を試験的に展開。その後、一般ドライバーの募集・参画を進めながら、サービス範囲を広げていく流れが予想されます。
さらに、配車システムやアプリ内決済など、Uberが世界で培ってきたテクノロジーを活用し、国内市場に最適化した形で“日本版ライドシェアモデル”を構築していくのではないでしょうか。
いずれにしても、Uberは日本国内でもライドシェアの本格展開に向けて動き出したといえます。すでに「Uber Eats」で築いたデリバリー市場での強固な基盤があるため、今後は「人の移動」分野でも同様に急速な拡大が期待されます。







